KOJIKI Talk

2014年10月、台本執筆中の ごまのはえと、古事記研究の専門家の三浦佑之先生とによる "古事記トーク" が実現しました!
前回公演『少年王マヨワ』のトークゲストにご出演いただいたご縁から生まれた、『カムサリ』を10倍面白くするスペシャルトーク。
どうぞお楽しみください!
ごま:国生みの兄妹神イザナキとイザナミ。二人は夫婦関係ですが、妹イザナミは火の神を生んだあとに命を落とします。ここで出てくる「神避り(カムサリ)」という言葉の意味が気になっているんですよね。

三浦:単純な意味としては、神様が去る、移動する。ここでは死ぬという意味でしょう。基本的に神は死なないので、姿はないけれど魂は存在している……というニュアンスでこの言葉になったんだと思う。 "隠れる" とか "避(去)る" という言葉は "死ぬ" と同義で使われますから。あの場面は特に、イザナミが黄泉の国(死者の国)、よその世界へ行ってしまう意味を持たそうと "神避り" という言い方をしていると考えることもできます。

ごま:あらためて考えてみると妻が急にいなくなる話って、小説やドラマなど、現代も文学のテーマとして良く扱われますね。
三浦:そうかもしれません。ここでは "イザナミの死体を見ない" という約束をイザナキが破ってしまい、夫婦関係が壊れるわけですが、例えば昔話の「夕鶴」なんかは、"機を織っている姿を見るな" というタブーを犯すことによって妻がいなくなる。神と人間、あるいは人間と人間ではないものとの結婚は異類婚と呼ばれ、最終的に離別し、元の世界に戻っていくのが基本的な形。もしかしたらこういったパターンを、現代の物語もずっと引きずっているのかもしれないですね。
ごま:イザナキとイザナミの話一つ取っても、古事記における死生観、人間観が垣間見える気がします。
三浦:そうですね。イザナキとイザナミは黄泉つ平坂(ヨモツヒラサカ)で、夫婦関係を破棄する宣言「言戸渡し(コトドワタシ)」をします。ここでイザナミが「1日に人間を千人殺す」と言ったのに対しイザナキは「じゃあ私は千5百の産屋を建てる」と答える。差し引き5百人ずつ人間が生まれ、増えていくと言っています。この神話のポイントの一つだと思うんですが、死の世界ではなく、死と誕生の循環を語る。古事記の死生観が強く出ていると思います。
また古事記では "人間=草" と考える。例えば地上で最初に生命を受けた神、ウマシアシカビヒコヂは、「立派な葦の芽の男」という意味で、泥から生えてくる葦、植物なんですよね。それが人間の誕生だとイメージしています。イザナキとイザナミも人間を "青人草(アオヒトクサ)" と呼んでいますし。雨の多い温帯モンスーンで緑豊かなアジアはこうやって、人間は草や木から生まれてきたと語る。砂漠地帯などの一神教的な世界で語られる創世記は、ヤーウェという絶対神がいて、自分の身体に似せて泥から人間を作ったと語る。風土性から来ている違いでしょう。
神話って単なるおとぎ話ではないので、ある意味では哲学であり、教訓であり、医学の知識でもある。人間は死ぬけれど、次の世代が生まれてくると考えれば、安心して死んでいけるでしょう? 人間は草であり循環する生命なんだというのは、仏教における輪廻転生とどこかでつながっていくのかもしれないけれど、その根幹的な発想をここに感じます。

ごま:仏教の輪廻転生よりも、古事記の人間観は素朴ですね。
三浦:身体的なものですよね。イザナミが死んで死体が腐乱している場面を「蛆たかれころろきて」って書いてますけれども、ありありと蛆のわく死体を描写している。人は腐って消える、だけれどもまた赤ちゃんはやってくる。そういう命の "めぐり" みたいなことを、生活に即したリアルな視点で語る。
ごま:なるほど、確かに。
三浦:この場面は面白いんですよ。古事記は基本的には漢文体なんですけれども、大事な部分はいわゆる万葉仮名で、一字一音を使って音仮名表記されている。「蛆たかれころろきて」もそう。「蛆虫がたかってコロコロいってて」というような意味です。今だったら "コロコロ" なんてかわいらしい擬音語ですけれど、今で言う "ゴロゴロ" とか、そういう言葉に対応する言葉だと思います。音のイメージが鮮明でしょう? 昔話の語り方や宮沢賢治なんかと同じですけれど、オノマトペと畳み掛けの言葉を古事記では非常に巧みに使い、リズミカルな形で文章を流していく。これは読んでいて面白いところですね。

ごま:一般的に、古事記および日本書紀は国家が編纂した、天皇の物語と言われますけれども……。
三浦:序文には、天武天皇が命令して国家が編纂してと書いてありますけれど、古事記は内容からみても、天皇の側に立って物語を語るような内容ではない。序文の言っていることはウソで、あとから付け加えられたのではないかと僕は解釈します。国家とは別のところにあったのが古事記、国家が作ったのが日本書紀。はっきり立場は違うと思う。古事記で語られるエピソードは、天皇とその一族のものばかりとは限りませんし。日本書紀は、古事記と同じ物語を歴史の中で天皇中心に描いていきますが、相違点を挙げていくとこの立ち位置の違いが説明できると思います。この前上演なさった舞台(13年に上演したニットキャップシアター 第33回公演『少年王マヨワ』)で扱ったマヨワの話もそうですよね。マヨワは、父を殺して王位についた大君アナホの仇討ちを果たし、臣下ツブラノオホミの家に逃げ込む。日本書紀では、この家に外から火をつけて焼いたと天皇の側に立って物語を語る。しかし古事記では、マヨワと臣下ツブラノオホミが屋敷の中で最期に対座する場面が描かれます。語り手の視点が敗れていく側にある。アフリカなどでも文化人類学の調査によれば、王の歴史を語っていく王直属の語り部と、外側を徘徊しながら一般の人たちに物語を語っていく人たちがいたそうですが、古事記もある意味、王家の物語をスキャンダラスな話として語っていたと考えられる。
ごま:それはやっぱり、敗れた側から語るほうが面白いからですかね?
三浦:そう、古事記はどうも語りとしての面白さを突き詰めようとしているのではないか、という気はします。具体的には分かりませんが、古代の日本には、折口信夫が盛んに強調した存在、 "乞食者(ホカイビト/祝福する人たちという意味)" がいたと言われています。要するに門付け芸人(人家の門口で芸を披露する芸人)です。そういう芸能者の存在が古事記にはかかわっているのではないかと予測される。実際は分かりませんが、市など人が集まる場所で演じられたりしたのではないか……今、駅前で音楽を演奏している人がいるでしょう、ああいう感じって、いつの時代もあるんじゃないかな。屋敷に呼ばれて演じたり、祭りで家々をまわって祝福したり。いろんな状況で演じられたと思う。
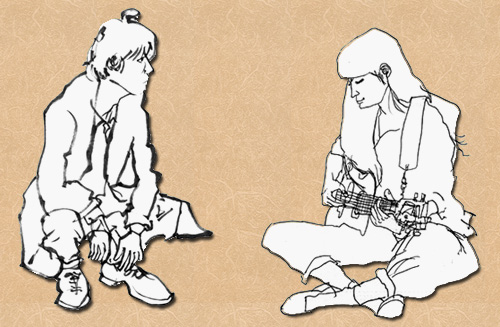
ごま:地理的には近畿地方ぐらいのエリアで活動したというイメージでしょうか?
三浦:都とその周辺にいた可能性は高いですね。関東まで流れてくるっていうのはちょっと考えられないですから。大和を中心とした村や街道沿い、難波から飛鳥への道筋なんかは、芸能者たちの道と共通している。古事記に「この蟹はいずくの蟹」っていう長い唄がありますけれど、あれはホカイビトが、蟹に扮して唄ったと考えられています。敦賀から都に移動しながら、蟹を貴族の食卓に並べて、蟹男と蟹女の恋物語を演じてみせたりする、そういう芸能者たちがいたって一向に不思議じゃない。鹿の唄も残っていますし、そういった食材を運ぶ道は活動エリアだったんじゃないでしょうか。
ごま:最後に、先生が古事記でお好きなエピソードを教えてください。
三浦:女性の物語は面白いですよね。中でもメドリ(女鳥)は好きです。5世紀のはじめ、オホサザキ(仁徳天皇)が天下を支配していた時の出来事です。大君オホサザキがメドリに求婚しようと、ハヤブサワケという使いを出す。でもメドリは使者のハヤブサワケに「あなたと結婚したい」って言って、二人で逃げるんです。結局、大君の軍に追いつかれて殺されてしまうんですけれども……。僕が学生時代に人気のあった映画「俺たちに明日はない」の主人公、ボニーとクライドにそっくりなんですよ。勝ち気な強い女の子と、振り回される男みたいな構図で、一人の女をめぐって二人の男がすったもんだするっていう典型的なドラマですよね。古事記には物語の核みたいなものが散りばめられていて、マヨワだってシェイクスピアの『ハムレット』そっくりです。もしかしたら物語の構造っていうのは古い神話なんかで出尽くしていて、現代の物語はそのバリエーションと言えるのかもしれない。そう考えて古事記を読んでいると、色んなことを思いつかれると思いますよ。
あとは、先ほどもお話ししたように、古事記は "滅びの物語" であり、それが面白い。神話の中で一番大きな滅びの物語は出雲の神々の物語です。オホクニヌシという少年が成長して、立派な王になって地上を支配しているけれど、結局は高天の原(タカマノハラ)の神様に制圧されてしまう。いわゆる「国譲り」と呼ばれる場面ですが、あれは征服戦争に負けてしまったわけです。敗れた側が出雲大社に祀られてオホクニヌシ(大国主)として讃えられる。古事記の神話の約4割が出雲の神々の物語で、そのほとんどが滅びの物語、滅びゆく者に対する鎮魂、悼みなんです。そこも古事記の大きな特徴であり、魅力でしょうね。
(構成・文=川添史子)
参考書籍:口語訳 古事記[完全版](文芸春秋)
[PROFILE] 三浦 佑之(みうら すけゆき)
国文学者(古代文学・伝承文学)、千葉大学名誉教授、立正大学教授。2003年、『口語訳 古事記』で第1回角川財団学芸賞を受賞。古事記ブームの火付け役となった。
Link: 神話と昔話-三浦佑之宣伝板-